日本の食文化としてのおせち料理の歴史や成り立ち、地域性に注目しながら、「家庭の魚料理調査」「お正月首都圏調査」「我が家のお正月食卓写真募集」「お正月に関するアンケート調査」4種類の調査結果に基づいて、“正月と魚食”をテーマに構成しました。
行商などの交易伝承や、庶民の信仰の旅などについて、民俗学の視点から研究をなさっている山本志乃さんに、調査の分析と解説をお願いしました。
HOME > 知る > 紀文のお正月 > 正月に関するデータベース > 正月と魚 ~ハレの日の家庭の食文化~ > 現代の正月


現代の正月
現代の正月の魚食
 「わが家のお正月食卓写真募集」等からわかるように、秋田の鰰焼き、福島のいか人参、茨城の鮒甘露煮、新潟の氷頭なます、岐阜の焼き鰯、京都の棒ダラの煮物、大阪のにらみ鯛、島根の赤貝(さるぼう)の煮物、下関のフグ刺身、長崎の湯かけ鯨など、いわゆる郷土料理や名物として知られる魚料理が散見されるのは興味深いところです。
「わが家のお正月食卓写真募集」等からわかるように、秋田の鰰焼き、福島のいか人参、茨城の鮒甘露煮、新潟の氷頭なます、岐阜の焼き鰯、京都の棒ダラの煮物、大阪のにらみ鯛、島根の赤貝(さるぼう)の煮物、下関のフグ刺身、長崎の湯かけ鯨など、いわゆる郷土料理や名物として知られる魚料理が散見されるのは興味深いところです。
また、寄せられたコメントからは、「毎年同じものを作る」あるいは「母から子へと伝えるもの」といった伝統へのこだわりが感じられます。全般的に標準化した現代の食生活のなかで、せめて正月くらいは地域や家の特徴を生かしたいという願いが反映しているのかもしれません。このように、何らかの魚介類が必ずといってよいほど含まれていることから、正月に魚を食べるという習慣そのものは、現代でも受け継がれていると考えることができます。
「家庭の魚料理調査」から鰤と鮭の現在
さらに、全国の20歳以上の既婚女性約4,931人を対象としたアンケート調査11「家庭の魚料理調査」から、正月に食べる魚介類の全国的な分布をみてみましょう。
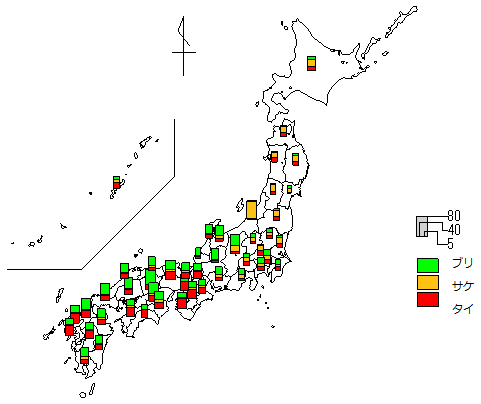
「家庭の魚料理調査」より、ブリ・サケ・タイの喫食件数の分布図
ここで注目したいのは、年とり魚として西日本と東日本をそれぞれ代表してきた鰤と鮭が、現代にあってもほぼ東西で分布を明確にしているということです。もちろん混在もあり、とくに首都圏のうちの東京・千葉・神奈川の3県では、鮭より鰤のほうがむしろ卓越しています。人口の流出入が激しい首都圏では、出身地の食文化の影響がこうした正月料理に表れているのかもしれません。
かつて、鰤と鮭が年とり魚として珍重されていた頃は、いずれも塩蔵処理が施された大きな魚として、正月の期間を食べつなぐ冬季の保存食の意味も持っていました。冷凍・冷蔵設備が整った現在では、生の切り身を入手することがほとんどです。鰤や鮭を食べるという伝統を、時代に合わせた食べ方に変えながら残しているのは興味深く、正月における食文化の保守性ともいえる一面が顕在化した結果となっています。

ブリ

サケ
正月・祝い・普段に食べている魚介類とその調理法
ただし、総数でみると、単独の魚種としては鰤が第1位で、5位の鮭とは大きく水をあけています。このことについて、魚の調理法からさらに詳しく実態を見てみると、鰤の場合は全体の7割近くが照り焼きもしくは塩焼きであり、他は刺身、煮付けなど、食べ方にさほどのバリエーションは感じられません。それに対して鮭は、スモークサーモンのサラダ、カルパッチョ、ムニエルなど洋食への展開が著しく、塩引き鮭の切り身を焼くといった食べ方を基本としていた年とり魚の時代に比べると、魚そのものを食するというよりは、魚を料理の具材のひとつとしてアレンジするという調理法へと多様化していることがわかります。
| 正月の魚 | 普段の魚 | ||
|---|---|---|---|
| 魚介類名 | 件数 | 魚介類名 | 件数 |
| ブリ | 918 | サケ | 1504 |
| タイ | 689 | サバ | 1289 |
| カズノコ | 459 | アジ | 835 |
| エビ | 416 | カレイ | 616 |
| サケ | 396 | イカ | 582 |
| マグロ | 251 | サンマ | 568 |
| イカ | 153 | ブリ | 557 |
| タラ | 133 | マグロ | 345 |
| ニシン | 127 | タイ | 299 |
「家庭の魚料理調査」より、正月・祝い・普段に食べている魚介類(抜粋)
| ブリ | サケ | タイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理法 | 料理名 | 調理法 | 料理名 | 調理法 | 料理名 | |
| 正月 | 焼く(605) | 照り焼き、塩焼き | 焼く(206) | 塩焼き、ムニエル、ちゃんちゃん焼 | 焼く(485) | 塩焼き、にらみ鯛、塩竃焼き |
| そのまま(163) | 刺身 | 漬ける(77) | なます、マリネ、粕漬け、南蛮漬け | そのまま(102) | 刺身 | |
| 煮る(93) | 甘辛煮、ブリ大根、煮付け | 煮る(43) | 昆布巻、酒粕煮、のっぺ汁 | 煮る(55) | 煮付け、甘辛煮、吸い物 | |
| 雑煮(29) | 雑煮 | そのまま(35) | 刺身 | 漬ける(26) | 南蛮漬け、酢漬け、昆布締め | |
「家庭の魚料理調査」より、ブリ・サケ・タイを正月・祝い・普段に食べるときの調理法と料理名(抜粋)

ちゃんちゃん焼
じつは、鮭は、「家庭の魚料理調査」によると、普段に食べる魚の第1位となっています。調理法の種類も、正月料理とさほど違いはありません。新巻鮭と氷頭といった一部の例を除いて、鮭はもはや特別な日の特別な魚ではなく、むしろ日々接する身近な魚という位置づけにあるといってよいでしょう。何よりも、普段に食べる魚の種類の多さが、水産物流通の広域化とともに、先の八尾市の女性が語った「毎日が正月だ」という言葉を実感させます。魚に限ってみれば、今日の私たちの食卓は、毎日がハレ化した状態にあるとも言えそうです。
※11.2011年8月実施のインターネットによる調査。
