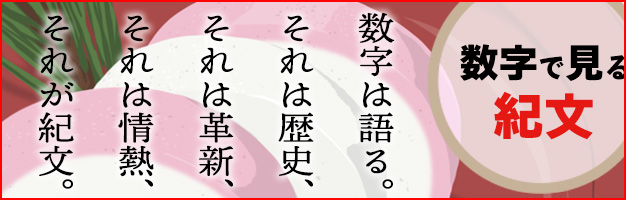日本の正月とおせち料理
いにしえより、日本では正月行事やその文化を大切にしてきました。正月とは新年の祝いをする行事で、歳神さまを迎え家族の幸せと五穀豊穣を祈る日です。
この時に食するものを「おせち料理」と言います。平安時代の宮中行事から1,000年の歴史の流れを経て、おせち料理は歳神さまへのお供え料理として、また、家族の幸せと五穀豊穣を願う縁起ものの料理をいただくものとして私たちの暮らしの中に定着していきます。
昔のおせち料理
全国の一般の方々のおせちは、明治・大正・昭和のはじめ頃までは、上の写真にあるような豪華なものは少なく、また、重箱に詰めるおせちやかまぼこなどの食材も都市部で見られるだけでした。
雑煮、年とり魚のサケやブリ、煮しめ、祝肴の黒豆、田作り、数の子・たたきごぼうなどの料理を食していたと言います。

紀文とおせち料理の発展

おせちの売り場に立つ創業者(時期:おせち事業を開始した頃)
1938年に創業した紀文は、この素晴らしい日本の食文化を全国の皆さまに伝え継ぎたいという思いから1950年におせちの主役である「かまぼこ」や「伊達巻」「よせもの」の本格的製造を開始、その後、取り扱いアイテムも増やしていきます。
その一方で、おせちを製造・販売するだけでなく、新聞・ラジオ広告などはもちろん、料理教室などのおせちの啓発活動にも注力してきました。
具体的は、1973年(昭和48年)から開始した消費者向け「おせち料理講習会」、海外初のおせち料理のイベントとして1981年(昭和56年)にはハワイ、翌年のロサンゼルスでの開催などです。
また、1974年(昭和49年)からスーパーマーケットなどの流通先を招待して、「お正月用商品発表会」を開始。ここでは商品紹介だけではなく、「年末年始の経済動向」「正月の文化とおせちの歴史」などの講演も行われました。
現代のおせち料理の発展に紀文が寄与したと言われるゆえんがここにあります。

おせち料理イベント(ロサンゼルス)
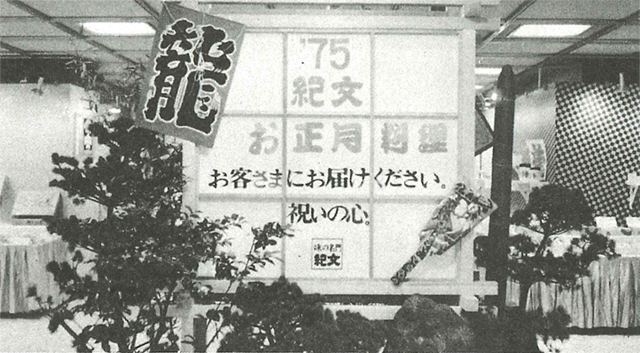
お正月用商品発表会(1974年)
おせち料理の数々

紅白かまぼこ
板に魚のすり身を盛りつけた後、蒸し上げたもの。山高で白く弾力のある食感を持つ。
かまぼこは「日の出」を象徴するもの。紅はめでたさと慶びを、白は神聖を表す。

伊達巻
魚のすり身に卵黄、砂糖などを混ぜて焼き、棒状に巻いた料理。
昔は文書や絵は巻物にしていたことから、知識が増えるという願いをこめて。

錦玉子
ゆで玉子を黄身と白身に分け砂糖などで味付け、裏ごしをしてから蒸した料理。
黄身は「金色」を、白身は「銀色」を表し財宝の意味もあり縁起が良い。

栗きんとん
ゆでたサツマイモやクリを砂糖で味付けをした後にペースト状にし、砂糖で味付けをした栗を混ぜた料理。
黄金色に輝く財宝にたとえて、豊かな1年を願う。

黒豆
黄大豆、青大豆など大豆の中の一つで種皮の色が黒色の大豆。醤油や砂糖で煮て食す。
「まめ」は元来、丈夫・健康を意味する言葉でおせち料理には欠かせない。

昆布巻
コンブを巻き、これをユウガオの果実を乾燥させたもので結び、しょうゆや砂糖で煮つけた料理。
一年を喜びながら生活できるように祈願する。

田作り
カタクチイワシの稚魚を干したものや、これをしょうゆ、みりんで煮詰めたものも指す。
古くからイワシを水田の肥料にしたことから五穀豊穣を祈願する。

数の子
ニシンの卵を塩漬けまたは乾燥させたもの。
ニシンの卵巣にはたくさんの卵が含まれるので、子孫繁栄の縁起物として。

菊花かぶ
カブに切り込みを入れ甘酢漬けし、切れ目を広げて、菊の花の形にする。
菊は神聖な花とされる、また。中国では古くから菊を不老長寿の薬草としており、それが日本に渡り、長寿を祈願する縁起の良い花となった。

小肌粟漬
ニシン科のコノシロを酢漬けにした後、クチナシで染めた粟で漬けた料理。
小肌はコノシロという魚の成魚になる前の名前。コノシロは成長過程で名前がかわり縁起が良いとされ、黄色の粟で五穀豊穣を願う。

えび
頭の付いたエビをだし汁、醤油、みりんで味付けした料理。
長いひげをはやし、腰が曲がっていることから老人を連想させ、長寿を祈願する。

するめ
イカを割いて内臓を抜き平らにして風をあて干したもの。
平安時代には宮中に献上されたほどの歴史のある食品。結納の品として使用され、めでたい祝儀の膳に欠かせない一品。

なます
ダイコンやニンジンを細切りにして酢や砂糖で味付けした料理。
お祝いの贈答品に紅白の紐を結ぶ「水引き」を結ぶ習慣があり、このニンジンの紅色、大根の白色の組み合わせが喜ばしいことから。

お多福豆
ソラマメを乾燥させた種実を水に戻し、砂糖やみりんなどで煮含めた料理。
ソラマメの形状が多くの福を呼ぶ顔の形「お多福顔」に似ていることから。

ごぼう八幡巻
やわらかく煮たごぼうを芯にして肉や魚を外側に巻いた料理。
細く長く地中にしっかり根を張るごぼうのように家や仕事がその土地に根付いて栄えることを願っている。